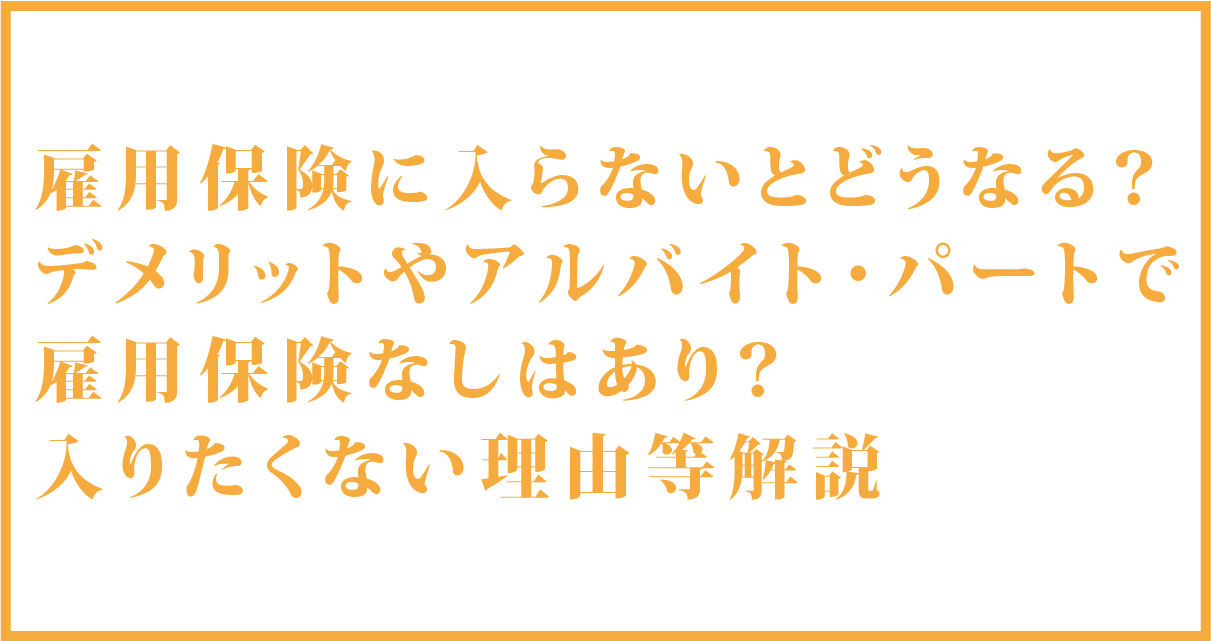 雇用保険に入らず仕事をする人は失業給付・育児休業給付・職業教育訓練給付・再就職手当などの給付は対象外となり、万が一の際の金銭的な補償が手薄となってしまいます。
雇用保険に入らず仕事をする人は失業給付・育児休業給付・職業教育訓練給付・再就職手当などの給付は対象外となり、万が一の際の金銭的な補償が手薄となってしまいます。
一般的な企業で労働者が負担する雇用保険料の保険料率は0.5%と低くなっています。厚生年金保険料・健康保険料にくらべて低額であり、毎月給料から天引きされるデメリットに比べ、雇用保険被保険者として万が一の際の補償が充実した労働環境で仕事をするメリットは大きいといえます。
雇用保険の加入には昼間学生を除く労働者・所定労働時間が1週間20時間以上・31日以上の継続雇用という3つの加入条件をクリアしなければなりませんので、これらの要件を満たさず雇用保険に入りたくても入れない場合もあります。
もし現在自分が雇用保険に入っているかが不明という場合には、給与明細で雇用保険料が天引きされているかを確認することのほか、ハローワークでの確認照会・雇用保険被保険者証等を確認するとよいでしょう。
雇用保険加入の記録は雇用保険被保険者番号により公的に管理されており、再就職の際にも原則は同一の雇用保険被保険者番号を用いて雇用保険に加入することになります。雇用保険被保険者証には加入手続きを行った企業名の記載もあるため経歴詐称等が発覚することもありえます。
- 雇用保険に入らないと失業・育児休業給付金を受け取ることができない
- 雇用保険に入らないと公共職業訓練制度・再就職手当の対象外となる
- 雇用保険に入るには3つの加入条件をクリアする
- 雇用保険の一般事業の利率は0.5%で労働者負担が低い
- 雇用保険の記録で職歴・経歴等が発覚する可能性がある
雇用保険に入らないとどうなる?デメリットは?
雇用保険の加入対象にならない週20時間未満等で働く方も多くいらっしゃるかと思います。ただ、雇用保険に加入しない場合、雇用保険料が天引きされない代わりに一定のデメリットがあります。
一番大きなデメリットは失業・出産等の万が一の際に、失業給付・育児休業給付などの所得補償を受けることができない点です。
失業や出産等の場合、すぐに収入の確保が難しい状況に置かれることも多く、雇用保険の給付金は生活の安定につながります。
またハローワークで申請できる教育訓練給付制度の費用や公共職業訓練期間中の技能習得手当も、雇用保険に加入し保険料を負担していた人以外は、受給対象外として受け取ることができません。
公共職業訓練(離職者訓練)は原則無料(テキスト代は実費負担)で就職に必要な職業スキルや知識を学び、キャリアアップや希望する再就職を実現するために有効な手段です。また、ハローワークによるキャリアコンサルティングや職業紹介などの就職支援が受けられるほか、一定の要件を満たせば基本手当(いわゆる失業手当)を受給しながら、それに加えて手当等が支給されます。
雇用保険に未加入の場合は、短期的に見れば給料から雇用保険料が天引きされず手取りが増えますが、労働者にとってそれが本当にメリットと呼べるかどうかは不明瞭です。
失業時や育児休業時期間中に給付が受けられない
雇用保険に未加入のまま仕事を続けてしまうと、離職後に失業給付を受給することができません。
- 雇用保険未加入の労働者は失業給付などの支援制度が受けられない
定年や雇用期間の満了、自己都合退職など失業の原因は多種多様であり、本人が会社を辞めるつもりがなくても会社が倒産したり、経営状況によっては、正規・非正規に関わらずリストラ対象として誰しも職を失う可能性もあります。一定期間以上雇用保険に加入していれば、失業中に生活の心配をしないで就職活動するための基本手当(いわゆる失業手当)を受給することができます。
また雇用保険に加入していれば、育児休業中で給与を受け取ることができない場合も育児休業給付を受給することができます。この給付は育児休業を取得すれば男性でも受給することができ、さらに令和4年10月からは産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した場合も受給することができるようになりました。
雇用保険に加入しない場合、働く人が直面する様々なピンチの際のセーフティネットを利用できないというデメリットがある可能性があります。
再就職時の公共職業訓練や再就職手当が使えない・もらえない
職を失い雇用保険を受給しながら再就職を希望する人が、公共職業安定所長から受講を指示される公共職業訓練(離職者訓練)は、在職中に雇用保険に加入していない人は利用できません。ただし、雇用保険を受給できない求職者であっても、原則無料の職業訓練(求職者支援制度に基づく認定職業訓練)は受講することができ、収入が一定以下の場合は給付金を受給しながら受講することができます。
- 雇用保険未加入の労働者は再就職で支給される各種給付制度を利用できない
基本手当(いわゆる失業手当)を受給する資格がある方は、早期に安定した職業に就いた場合、再就職手当などの就職促進給付を受け取ることができます。
離職後の公共職業訓練については、雇用保険の受給ができない方も受講することができますが、同じくキャリアアップのための制度である教育訓練給付制度は、雇用保険に加入している被保険者が受給できる制度です。
教育訓練給付制度は働きながら、専門・実践的な知識やスキルを学びスキルアップや資格取得を目指すための認定講座を受講・修了した場合に、受講費用の一部(最大で70%)を受け取ることができます。
これはスキルアップやキャリアチェンジを目指す労働者が主体的に教育訓練を受講・修了した場合に費用の一部が支給される制度で、大学院などの課程や、業務独占資格の取得を目指す講座など、より専門的・実践的な学びを目指す場合に利用することができます。対象者は過去に原則として1年以上雇用保険に加入し保険料を負担していた人になります。
教育訓練給付の対象となる教育訓練は、数か月から数年にわたるものも多く、雇用保険に未加入の労働者は、在職中にステップアップとして長期にわたる講座の受講を考えた際に費用の補助を受けることができなくなります。
給与の手取り額を優先し雇用保険に入らない働き方を選択をする場合、雇用保険に加入していれば受けられた支援制度を受けることができないことを知っておきましょう。
雇用保険に入りたくない理由
雇用保険未加入の状態で労働することは多くのデメリットがあると理解していても、実際に雇用保険に加入することに抵抗を感じる人もいるかもしれません。
雇用保険に入りたくないと考える労働者は、毎月の給料から雇用保険料が徴収され手取りが減ることに抵抗を感じているのかもしれません。
あえて雇用保険に加入するメリットを感じない方もいらっしゃるでしょう。
また短期間に就職退職を繰り返す場合は、頻繁にハローワークへ出向いて手続きすることが面倒に思われるかもしれません。
短期的な視点では一見デメリットがある雇用保険ですが、長期的な視点で考えればメリットが上回るため、雇用保険に入りたくないからという理由で所定労働時間を短くするといった選択をすることはおすすめできません。
給料から天引きされるので手取り収入が減る
雇用保険に加入すると毎月の給料から自動的に雇用保険料が天引きされるので、実際に労働者に支給される手取り金額が減少します。
- 雇用保険料が給料から徴収され手取りが少なくなる
雇用保険料は会社の給料から徴収されるので、労働者が毎月個人で納付する必要はありません。また、会社は被保険者負担分と比べて保険料率が大幅に高い保険料を支払っており、これによって前述の充実した各種給付を受けることができています。
しかしいわゆる失業手当に比べて、それ以外の様々な給付や支援制度はあまり知られていないため、将来の恩恵に対する実感がわきづらく、収入が減らされることを嫌って雇用保険に入りたくないと思う人がいるようです。
アルバイト・パートで雇用保険の加入対象になるかどうかは雇用条件により決まる
労働者が雇用保険に加入するには大きく3つの条件を満たす必要があり、労働条件によっては雇用保険に入りたくても入れない場合があります。
昼間学生を除く労働者であって、週の所定労働時間が20時間以上の雇用条件で、31日以上の雇用が見込まれる場合、雇用主は対象となる労働者を雇用保険に加入させなければ法律違反として処罰されることがあります。
しかし、被保険者負担分に比べ事業主負担分の雇用保険料率は高く設定されているため、勤務先によっては雇用保険の加入条件を満たさない範囲で、週の所定労働時間を短く設定した労働条件で募集していることもあり、加入を希望するすべての労働者が雇用保険に加入できるわけではありません。
雇用保険加入条件
雇用保険の適用事業所に雇用される労働者は、パートやアルバイトなどの雇用形態や、事業主や労働者の加入希望の有無にかかわらず、下記の条件のいずれにも該当する労働者は原則としてすべて被保険者になります。
- 雇用保険の3つの加入条件
①昼間学生でないこと
②1週間の所定労働時間が20時間以上であること
③31日以上の雇用見込みがあること
会社は加入に対して法的義務があり、罰則を受けることがある
会社は前述した3つの雇用保険加入条件を満たす労働者を雇用した場合、加入させなかったりまたは偽りの届出をしたりした場合、雇用保険法第八十三条に基づき罰則の対象となります。
第八十三条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第七条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合
二 第七十三条の規定に違反した場合
三 第七十六条第一項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合
※雇用保険法八十三条第四・第五は割愛(引用:雇用保険法 – e-Gov法令検索)
雇用保険料率は0.5%と健康保険料や厚生年金保険料に比べ低額であり加入のメリットが多い
雇用保険料率は、事業の種類によって定められています。
雇用保険料率が高くなればその分、毎月給料から天引きされる雇用保険料も高くなりますが、2022年10月以降の雇用保険料率は9月までに比べ労働者負担分の利率は0.2%増加しているとはいえ、雇用保険料率はそれでも0.5%と低額であるのに対しで多様な支援制度が受けられます。
雇用保険料率は事業の種類によって異なり、被保険者負担分は一般の事業は0.5%、農林水産・清酒製造の事業は0.6%、建設の事業は0.6%となっています。
雇用保険に入っているか調べる方法
現在自分が雇用保険に加入しているかどうか不明という場合には、確認するために3つの選択肢があります。
まず一つめは、ご自身の給与明細を確認し、雇用保険料として給料から天引きされているかどうかを確認します。
雇用保険に加入していれば、控除項目に天引きされる雇用保険料が記載されています。
二つめは雇用保険被保険者証・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)で、雇用保険の加入の有無を確認する方法です。
上記は雇用保険資格取得届が提出されると、ハローワークから事業主を通じて労働者へ交付される書類です。
三つめはハローワークで雇用保険の確認照会をおこなう方法です。
雇用保険被保険者資格取得確認通知書を事業主に照会したが、被保険者証等が交付されない場合や、事業主への照会が困難な場合、または被保険者証等の記載事項と事実が異なる場合などに確認できます。
原則として事業所の所在地又は照会者の住居所を管轄するハローワークに雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票等を提出して行います。本人が加入照会を行いますが、代理人が行う場合は委任状が必要です。
万が一、会社の問題で、雇用保険の被保険者となる労働者を雇い入れたにもかかわらず、資格取得の手続きが行われていななかった場合、失業手当を受給する際に重要となる「被保険者であった期間」の要件を満たさないなど、不利益を被る可能性がありますので、加入しているかどうかはご自身でも確認しておくとよいでしょう。
給与明細で控除されているかチェックする
アルバイトなどの雇用形態で働いている場合、雇用開始時点では週の所定労働時間が20時間未満で契約しており雇用保険に加入していなかったが、契約期間の途中や契約更新時に週の所定労働時間が長くなり、雇用保険に加入することになったというケースもあります。
雇用条件通知書や雇用契約書にも加入の有無は記載されていますが、給与明細の控除欄で確認するのが手軽でしょう。
「雇用保険被保険者証」と「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」があるか確認する
事業主が雇用保険資格取得の手続きを行うと、ハローワークから、雇用保険被保険者証・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用・事業主通知用)と呼ばれる書類が交付されます。
この書類は事業主を通じて労働者に交付されるものですので、雇用保険被保険者証・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)を受け取っているか確認しましょう。
事業主は雇用保険の被保険者となる労働者を雇い入れた場合は、管轄のハローワークに雇用保険被保険者資格取得届を提出し、ハローワークが交付する雇用保険被保険者証・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)を労働者に渡すこととなっています。
給料明細では雇用保険料が天引きされているのに雇用保険被保険者証等を受け取っていない場合、事業主が保管している可能性もあるので確認してみましょう。
ハローワークで確認照会を行う
本人が希望すればハローワークを通じて、現在の雇用保険の状況を確認することができます。
- 本人がハローワークで確認照会し雇用保険の加入状況を確認する
この方法は雇用契約書等や給与明細が手元になく、また事業主に照会できない場合等に雇用保険の加入状況を確認したい場合に有効です。
確認照会はどこでもできるという訳ではなく、原則として事業所の所在地又は自分が住んでいる地域のハローワークで行います。
確認照会には雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票に本人・住所確認書類を添付しますが、代理人が行う場合は委任状も併せて提出します。
雇用先の会社が雇用保険の加入手続きを適正に行っていれば問題ありませんが、確実に雇用保険の加入状況を確認できる方法です。
雇用保険から経歴詐称等がバレる可能性がある
事業主が労働者の雇用保険加入の手続きをおこなうと、厚生労働省・管轄ハローワークが管理しているデータベースに雇用保険の加入情報が記録されます。
採用時に提出する雇用保険被保険者証には雇用保険被保険者番号・前職で加入手続きを行った会社名や資格取得日が記載されています。
採用面接で提出する履歴書・職務経歴書に記載した前職の社名や入社日と、雇用保険被保険者証に記載された内容に差異があれば、経歴詐称を疑われる可能性もありえます。
転職する際に、このようなトラブルにならないためにも雇用保険の資格取得時には雇用保険被保険者証等でご自身でもしっかりと加入を確認しておきましょう。
この記事の監修社会保険労務士 |
寺島 有紀 |
|---|---|
| 事務所名 | 寺島戦略社会保険労務士事務所 |
| 所属社会保険労務士会 | 東京都社会保険労務士会 千代田支部 (登録番号 12180023号) |
| 備考 | 雇用保険加入に関する記事を監修 |
- TOPへ戻る >>株式会社トイント
